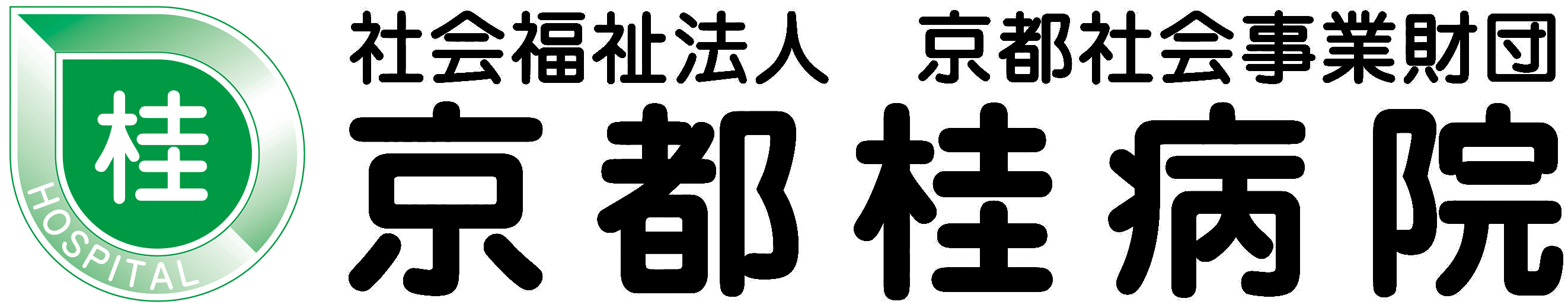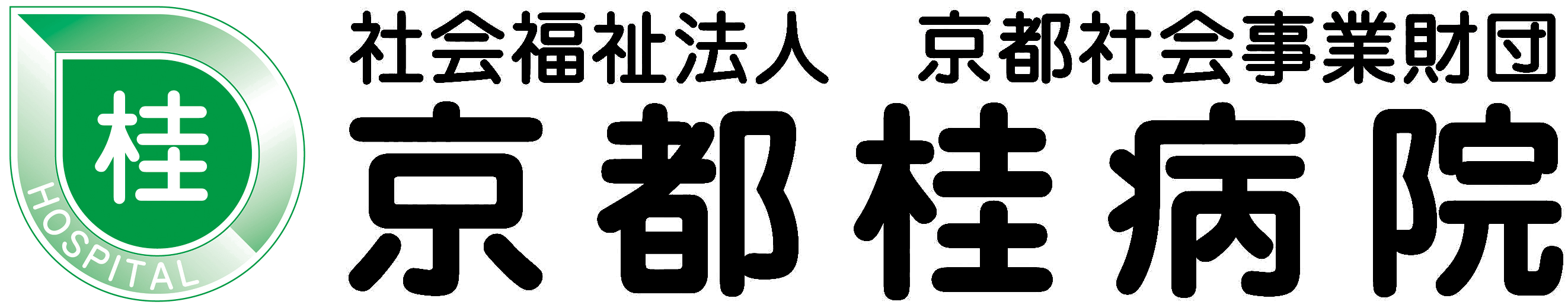部門ブログ
- 栄養部門 旬彩だより4月号
- 栄養部門 NST新聞春号
- 薬剤部門 新しく仲間が増えました!
- 栄養部門 春のおとずれ
- 薬剤部門 論文がアクセプトされました!
- 栄養部門 春を告げる魚
- 栄養部門 旬彩だより3月号
- 栄養部門 春分の日
- 栄養部門 WKD in KATSURAレポート!
- 栄養部門 NST&せん妄・認知症ケアチーム合同特別講演会
- 栄養部門 旬彩だより4月号
- 栄養部門 NST新聞春号
- 栄養部門 春のおとずれ
- 栄養部門 春を告げる魚
- 栄養部門 旬彩だより3月号
- 栄養部門 春分の日
- 栄養部門 WKD in KATSURAレポート!
- 栄養部門 NST&せん妄・認知症ケアチーム合同特別講演会
- 栄養部門 第1回丹後地区 腎臓病市民公開講座
- 栄養部門 ひな祭り
- 救急科 救急現場と人生会議
- 救急科 2024年度救急科スタッフ大募集!
- 救急科 4,5月のこってり研修医学習会
- 救急科 2023年度桂ERxCCM始動!
- 救急科 新棟稼働し気付けば3月
- 救急科 新棟内覧会
- 救急科 重症病態における急性期栄養療法とRFS予防
- 救急科 地域連携セミナー2022
- 救急科 今までの50年、これからの50年
- 救急科 京都新聞健康生活講座で登壇しました